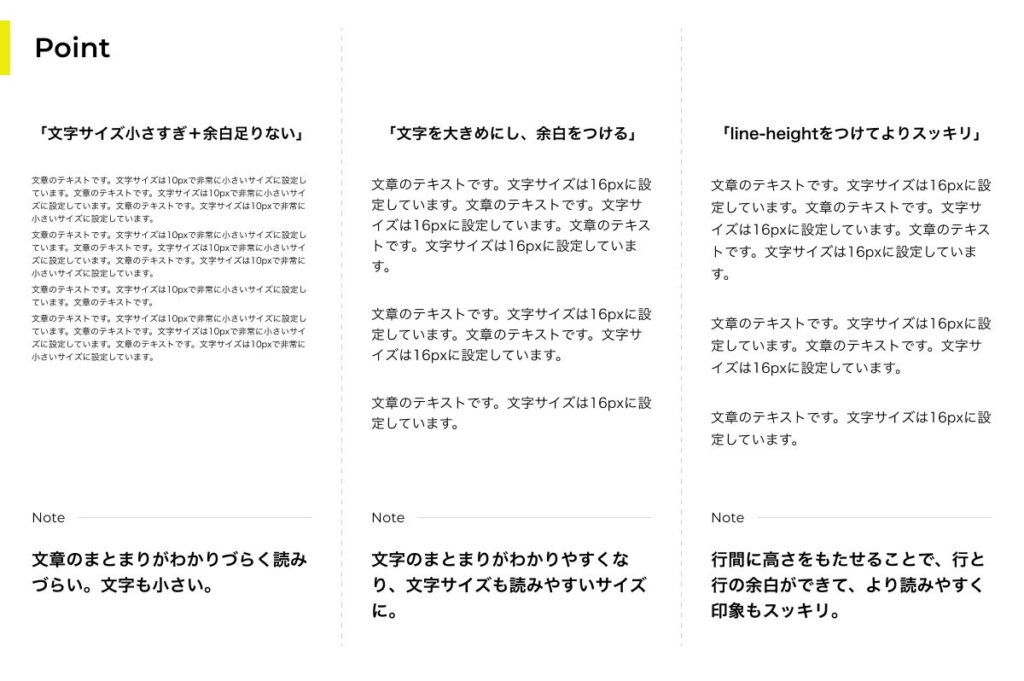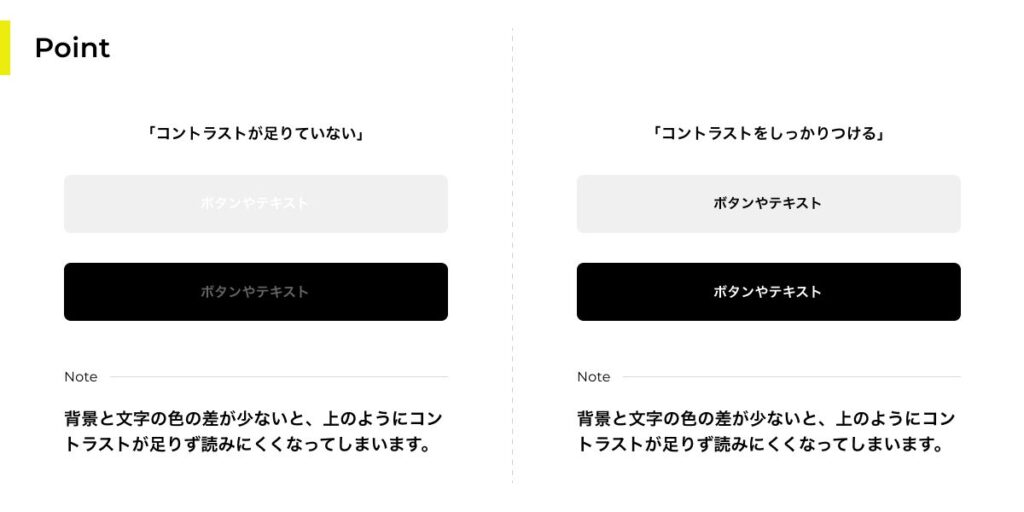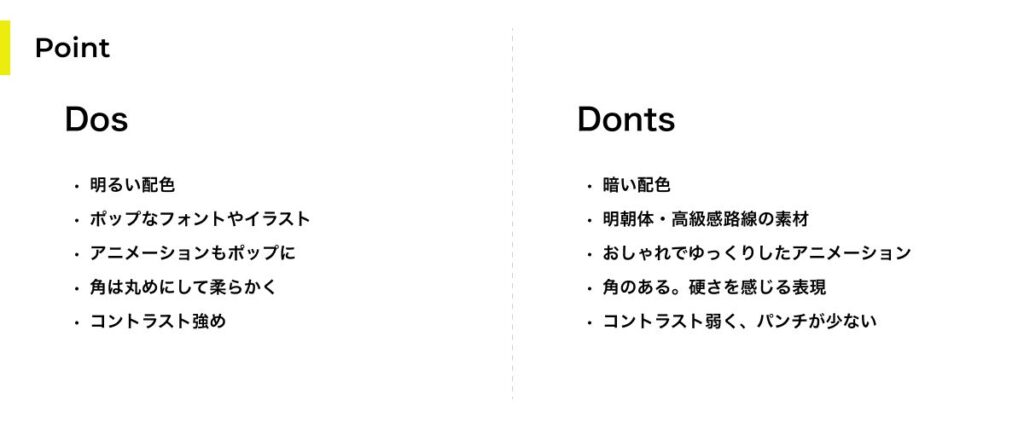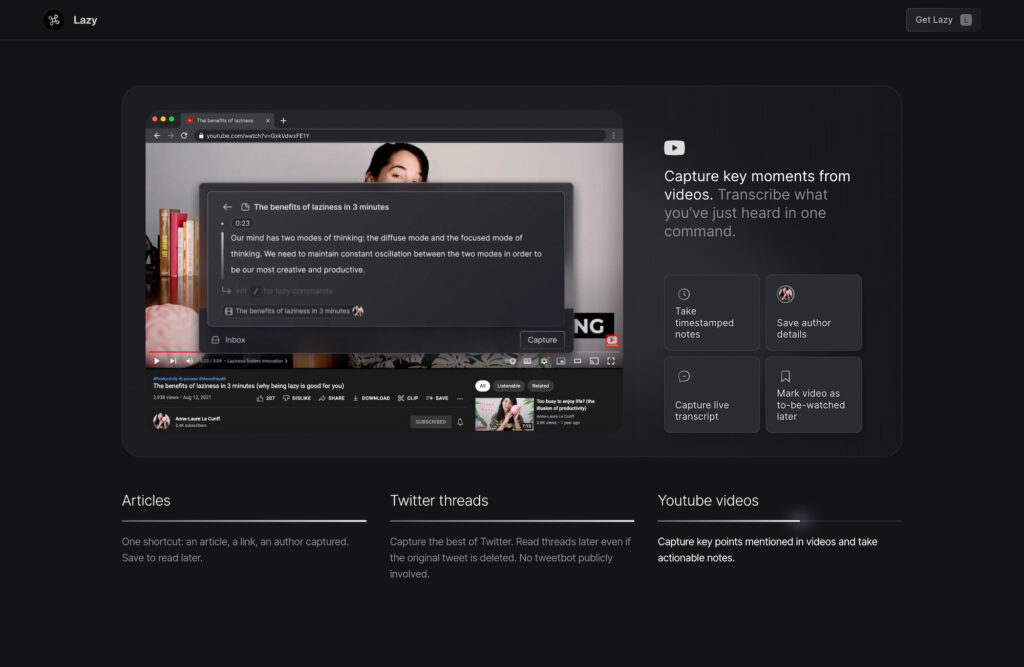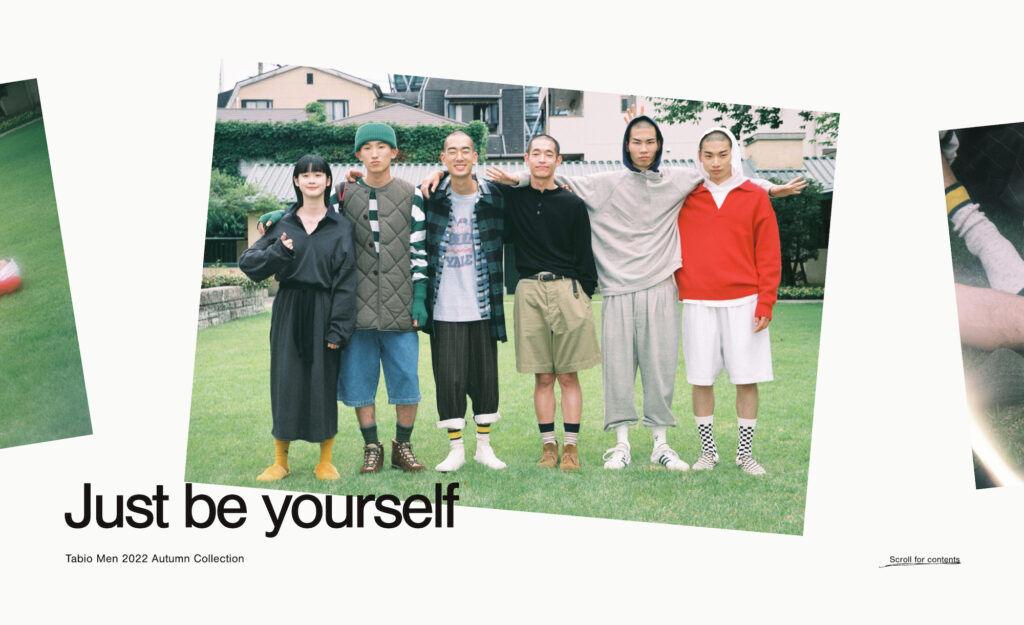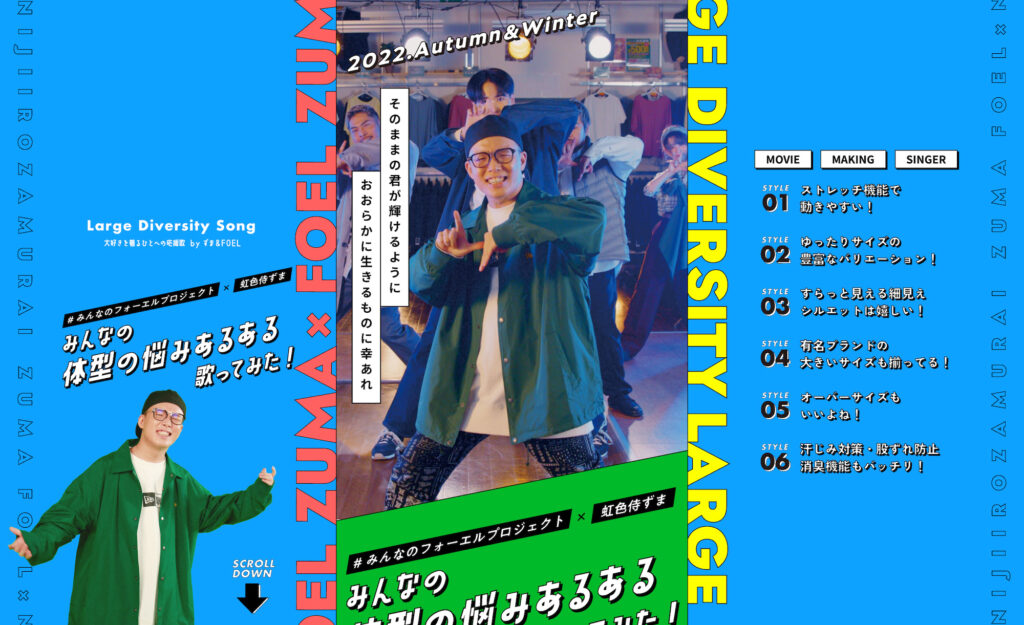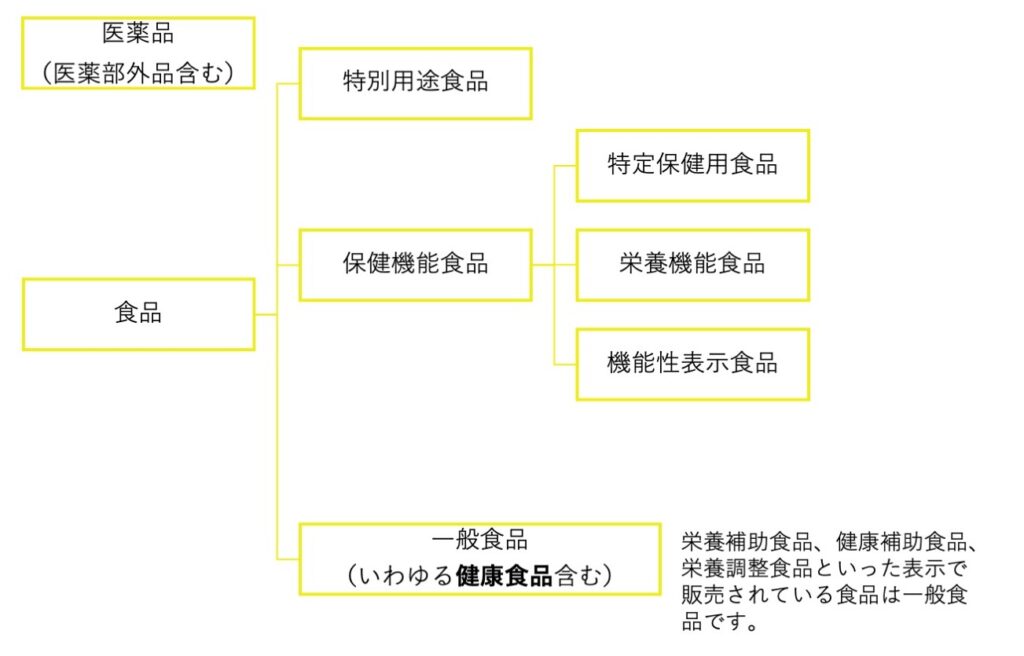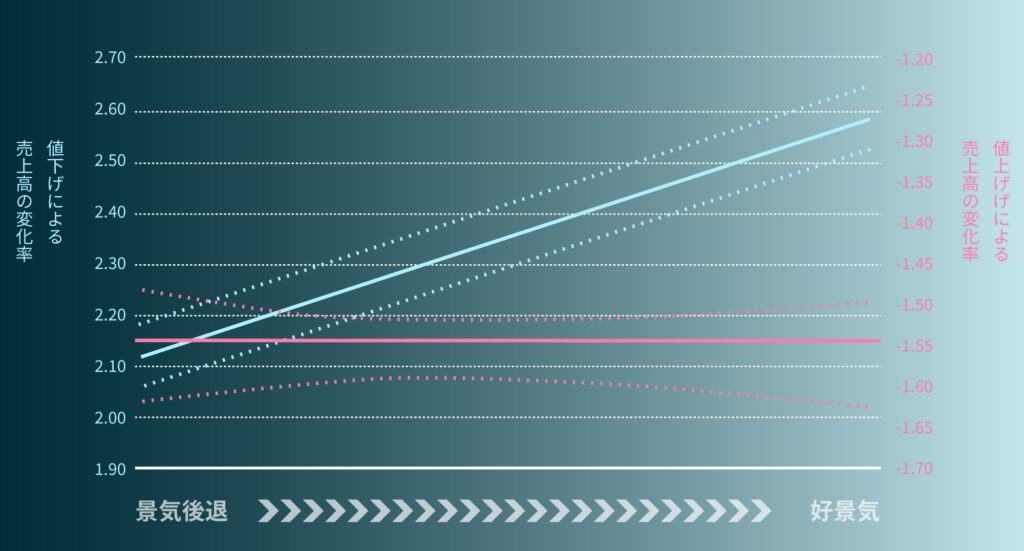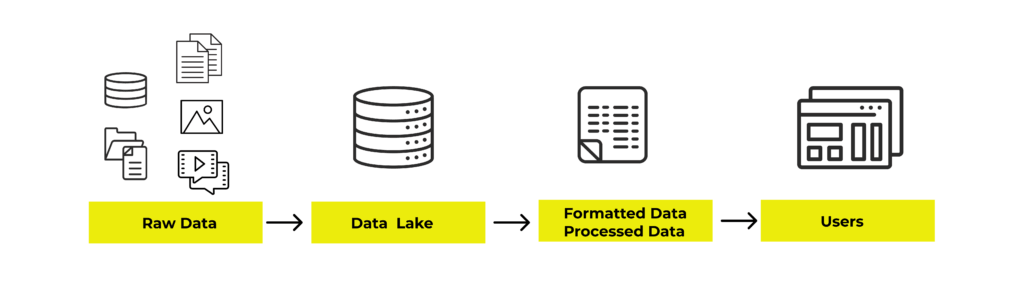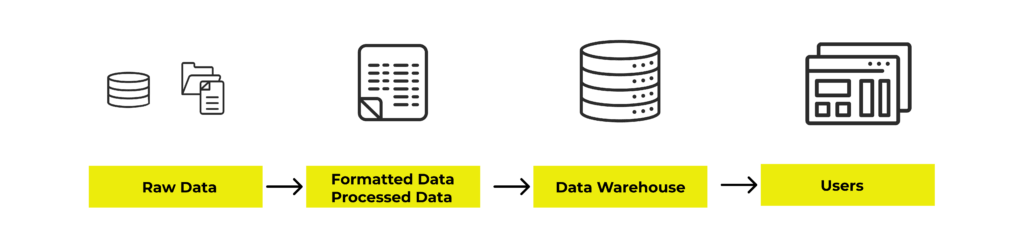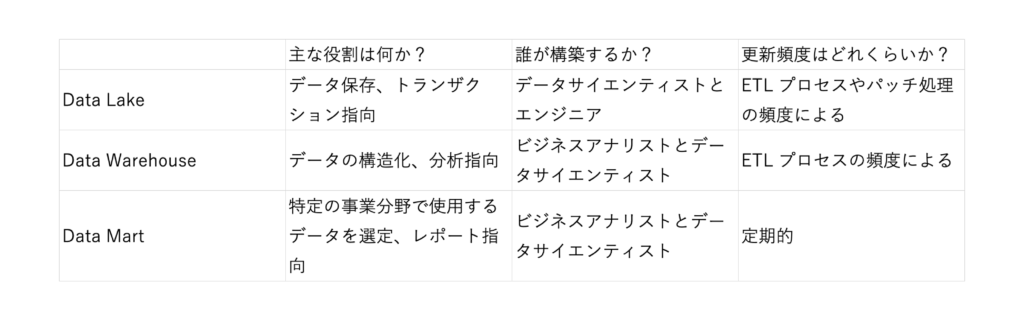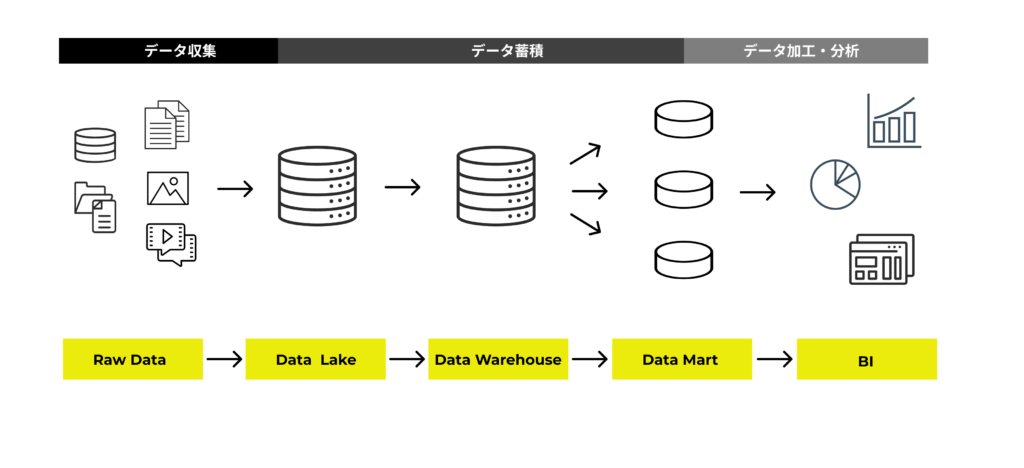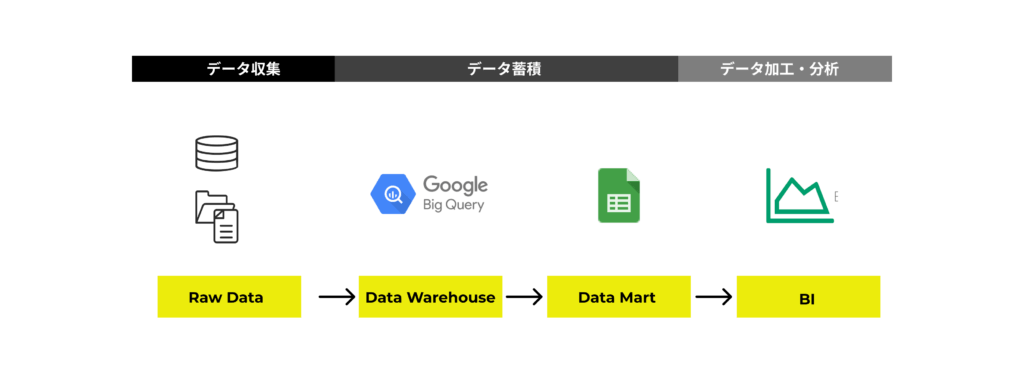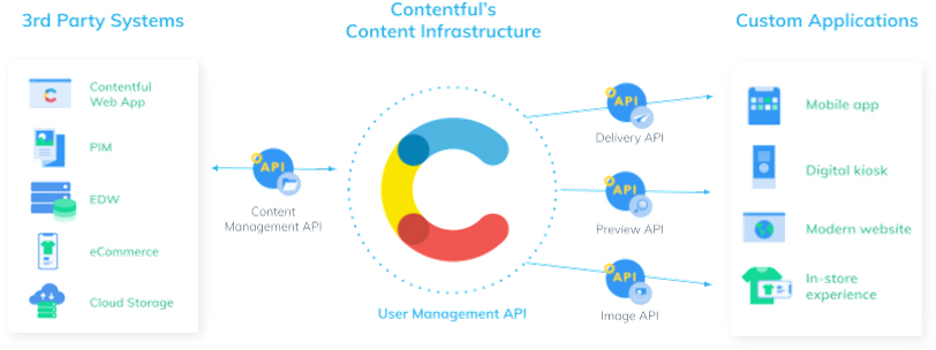「ステマ」規制への対応…日本と欧米の規制内容はどう違う?
消費者庁は2023年10月1日、景品表示法による「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制を開始します。一方、欧米などでは早くから規制を導入し、ステマを厳しく取り締まってきました。
消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」(京都大学大学院法学研究科のカライスコス アントニオス准教授が報告)で議論された内容などを参考に、EU・米国のステマ規制の概要と、日本との違いについて見ていきましょう。
米国、スポンサー契約の有無などの開示を要求
米国のステマ規制は、米国連邦取引委員会(FTC:Federal Trade Commission)が所管する「連邦取引委員会法」が、中心的な役割を果たしています。
商取引に影響を与える「不公正または欺瞞的な行為」をFTC法第5条で違法と定め、ステマについては各種ガイドラインと合わせて規制しています。
同法が禁止する違法行為については「欺瞞(ぎまん)に関する執行指針」により、消費者を誤認させるような表示を行うこと、表示が消費者の購買行動に影響を与えること、などと説明しています。
ステマなどに特化した「ニュースとしての形態を有する広告に関する勧告的意見」では、広告やプロモーションを行う場合、広告であることを識別できるようにしなければならないと定めています。
これに加えて、2015年の「欺瞞的な形態の広告に関する執行方針」により、取り締まりの方針が一層明確にされました。商品を推奨しているコンテンツ(記事)を広告と認識できない場合、消費者は誤認してしまうため、スポンサー契約の有無などを開示しなければならないと規定しています。
米国ではインフルエンサーなども規制の対象に
米国のステマ規制は、各種ガイドラインで補足されています。「広告における推奨及び証言の利用に関する指針(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising)」は、2009年に更新され、インフルエンサーマーケティングにも適用できるものとなりました。
商品の推奨は、推奨者の正直な意見を反映しなければならないとし、明示的であっても暗示的であっても欺瞞的な行為を禁止しています。
広告における推奨及び証言の利用に関する指針の内容
現行規制では、基本的な条項は4つにです。
- a)Endorsements must reflect the honest opinions, findings, beliefs, or experience of the endorser. Furthermore, an endorsement may not convey any express or implied representation that would be deceptive if made directly by the advertiser
訳)商品やサービスの推薦は、正直な意見、調査結果、信念、または経験を反映する必要があります。広告主が直接作成したら、欺瞞となるような推薦は明示でも黙示問わず、推薦者を介しても伝えることはできません。
- b)The endorsement message need not be phrased in the exact words of the endorser, unless the advertisement affirmatively so represents. However, the endorsement may not be presented out of context or reworded so as to distort in any way the endorser’s
訳)推奨コメントは、肯定的に表現しない限り、推奨者がコメントをそのまま表現する必要はありません。ただし、推薦者の意見や製品に関する経験を何らかの形で歪めるために、推薦を文脈から外して提示したり、言い換えたりすることはできません。
- c)When the advertisement represents that the endorser uses the endorsed product, the endorser must have been a bona fide user of it at the time the endorsement was given. Additionally, the advertiser may continue to run the advertisement only so long as it has good reason to believe that the endorser remains a bona fide user of the product.
訳)推奨者が製品を使用したことを示す広告・宣伝を行う場合、推薦の依頼を受けた時点でその製品のユーザーである必要があります。さらに、広告主は、推奨者が製品のユーザーであり続けると信じる十分な理由がある場合に限り、広告を掲載し続けることができます。
- d)Advertisers are subject to liability for false or unsubstantiated statements made through endorsements, or for failing to disclose material connections between themselves and their endorsers.
訳)広告主は、推奨コメントの虚偽または根拠のない声明、推薦者との関係を開示しないことに対して責任を負います。
同指針では、推奨者は実際に商品を使用した経験のある者でなければならないと規定。広告主に対しては、推奨を通じて虚偽の説明を行った場合や、推奨者との関係を開示しなかった場合に責任を負うとし、推奨者も責任を負うことがあるとしています。
日本の景品表示法によるステマ規制は、商品を推奨したインフルエンサーなどを規制の対象外としていますが、米国では責任が問われ、この点が大きく異なると言えます。
また、米国連邦取引委員会(FTC)のガイドラインは、シンプルで非常にわかりやすいです。日本の規制は、規制対象を明確にはしているものの、本質的なことが少し抜け落ちてしまっているようにも感じます。
こういった規制の本質は「嘘をついて販売してはいけない!そして消費者に損をさせてはならい!」ということが目的だと思いますが、日本のステマ規制では消費者保護の視点の要素が足りないようには感じます。もう少し本質的な部分に対して記載した方がロジカルな規制になり、わかりやすいのかもしれません。
広告と明記することも大事だとは思いますが、「本当のことを言っているか、信念に基づいているか」が本来はポイントになるような気はします。信念に基づかないコメントでも広告と表示すればOKになってしまいますからね。
EU…禁止行為を「ブラック・リスト」で示す
EUのステマ規制の概要を見てみましょう。「不公正取引方法指令2005」が取引全般を規制し、ステマも規制対象に含まれています。この法律は、取引の前後も含めて幅広く規制するという特徴があります。
次に、不公正な取引方法の典型として、「誤認を招く取引方法」や「攻撃的な取引方法」を禁止しています。
さらに、問題となる取引方法を具体的に示すために、「ブラック・リスト」を用意しています。
ブラック・リストには、「販売促進を目的に、メディアに費用を支払ってコンテンツを使用したにもかかわらず、広告であると明示していない」、「上位に表示するための有料のランキング広告であることを明確にせずに、検索結果を提供」、「商品の宣伝を目的に、消費者による虚偽のレビューを投稿」などの5項目を挙げています。
このようにEUでは、ステマを各段階で幅広く規制しています。仮に、ブラック・リストの5項目に該当しない場合であっても、法の趣旨を踏まえ、不公正な取引に当たるかどうかを判断します。
日本の景品表示法によるステマ規制も包括的であり、抜け道を防ぐようにしています。この点はEUの法体系と共通しています。
EUはデジタルプラットフォーム運営事業者も規制
EUではこのほかにも、「視聴覚メディア・サービス指令による規制」によって、商業的な情報である場合にはその旨を明確化すること、スポンサー契約の存在を明示すること、などを規定しています。
また、「電子商取引指令」に置き換わる予定の「デジタルサービス法」では、デジタルプラットフォーム運営事業者に対し、プラットフォーム上の広告について次の3点を求めています。
- 提供された情報が広告であることを明示。
- 広告主を明示。
- 広告費を支払った者が広告主でない場合、支払った者を明示。
一方、日本のステマ規制の根拠となる景品表示法は、デジタルプラットフォーム運営事業者を規制の対象外としています。この点はEUの規制と大きく異なります。
将来的に米国・EU並みの措置が検討される可能性も
ここまで見てきたように、米国ではインフルエンサーといった推奨者も取り締まりの対象とし、EUではデジタルプラットフォーム運営事業者にもステマ対策を義務づけています。一方、包括的にステマを取り締まるというスタンスは、米国・EU・日本に共通した点です。
ステマ規制の在り方を議論した消費者庁の検討会では、インフルエンサーやデジタルプラットフォーム運営事業者への対応が課題に上ったものの、最終的には見送られました。しかし、今回導入した規制では効果がないと判断された場合、将来的に米国やEUのような厳しい措置が検討される可能性も出てきそうです。